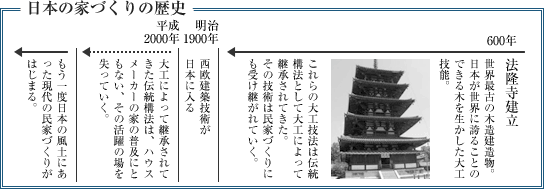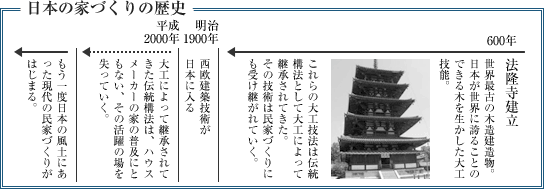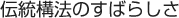
 伝統構法の良さは、なんと言っても「木組み」にあります。特に雪国新潟では、地元の粘り強い木を組み、雪の重さに耐える丈夫な家を作らなくてはいけない。そのためには、大工が木のことをちゃんと知っておかなくてはならない。「木のクセを読む」と言いますが、その通りで、2・3年かけて乾かした木でも、年を経るごとに反りが出てくる。それを想定しながら、知恵を絞って木材を組んでいく、そこに伝統構法の醍醐味があると言えます。 伝統構法の良さは、なんと言っても「木組み」にあります。特に雪国新潟では、地元の粘り強い木を組み、雪の重さに耐える丈夫な家を作らなくてはいけない。そのためには、大工が木のことをちゃんと知っておかなくてはならない。「木のクセを読む」と言いますが、その通りで、2・3年かけて乾かした木でも、年を経るごとに反りが出てくる。それを想定しながら、知恵を絞って木材を組んでいく、そこに伝統構法の醍醐味があると言えます。
職人は、とにかく長持ちする家を作ることに全身全霊を捧げます。伝統構法とは、つくり手にとっても、本当にやりがいのある魅力的な工法なのです。
 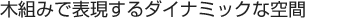
 ダイナミックな空間、それは「木」一本一本の個性が発揮された時、はじめて生まれます。
ダイナミックな空間、それは「木」一本一本の個性が発揮された時、はじめて生まれます。
木は一本一本育ちが違います。中でも曲った木は、使い方を工夫すれば真っすぐな木の何倍もの強さを発揮します。一見弱そうだったり、細かったりする木でも、自分の力を発揮できる場所に使われると、持って生まれた素晴らしい表情を見せ、見事にその役割を果たすのです。
木組みが表現するダイナミックな空間は、日本古来の構法ゆえに生まれる、世界に誇れる空間なのです。
 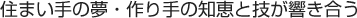
 まず、家をつくるにあたり、住まい手、設計者、大工の三者で「徹底的」に打合せをします。住む人あっての家づくりですから、施主さんの要望は出来る限り全て取り入れ、その実現のために設計者と大工は知恵を絞ります。無茶な希望があれば、ここできちんと説明して納得してもらいます。このプロセスを三者が一緒に歩むことで、施主さんには、設計者と大工の考え方や技量が自然と伝わって行きます。 まず、家をつくるにあたり、住まい手、設計者、大工の三者で「徹底的」に打合せをします。住む人あっての家づくりですから、施主さんの要望は出来る限り全て取り入れ、その実現のために設計者と大工は知恵を絞ります。無茶な希望があれば、ここできちんと説明して納得してもらいます。このプロセスを三者が一緒に歩むことで、施主さんには、設計者と大工の考え方や技量が自然と伝わって行きます。
一般の住宅と比べ、時間と手間がかかるのは確かですが、完成した時は、施主さんはもちろん、つくり手の感慨もひとしおです。
|